夏休み自由研究応援講座「小さな研究者になろう!~まちの中の樹木調査隊~」の第1日目を開催しました!

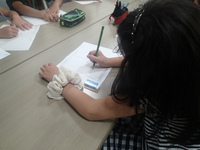














この日初めて会った子どもたちも多いので、まずは簡単な「文字合わせ」のゲームで遊びました。
一人一文字のカードを持ち、「2文字の言葉」というお題が出たら自分の文字と組み合わせたら言葉ができる文字を探して言葉を完成させます。
頭をフル回転させて、言葉を見つけ出します。
頭が柔らかくなったところで、いよいよプログラムがスタート。
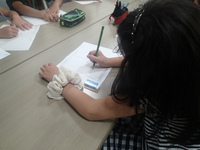
まずは「木ってどんなだったけ?」ということで、各自「木」の絵を描いてみました。
「葉っぱってどう生えてるの?」「木の幹ってどんな模様?」考えながら描き進めて、いろいろな木の絵が完成!

本物の木を見に行く前に、この講座で講師として来ていただいた櫻井善文さん(ニックネームは"ぜんぜん"!)のお話を聞きました。
ぜんぜんは、株式会社ドーコンで植物の調査をしているプロの方。
普段はどのような植物調査をしているのか聞きました。
調査で使う"プロの道具"に子どもたちも興味津々!
プロの道具とはちょっと違うけれど、今日使う調査道具を持って、いよいよフィールドワークへ出発!

札幌エルプラザの玄関を出たところにすぐ街路樹を発見。
葉っぱの付け根の形に特徴がある木で「ハルニレ」だと教えてもらいました。

地図に番号を落として・・・

調査票にその番号と木の特徴を記録して・・・
押し葉にするために葉っぱを1枚いただいて、その葉にも番号を付けて「調査研究袋」にしまいます。
調査ってなかなか大変!

それでも、次の木を見つけると樹皮の様子や葉っぱの特徴などを観察して次々と記録していました。

木の名前を教えてくれたのは最初の「ハルニレ」だけ。
あとで図鑑を使って名前を調べるので、そのヒントになりそうな特徴をしっかりメモ!
調査票に書ききれず、自分のメモ帳に記録する人も!
真夏の暑さの中、札幌エルプラザの周りをぐるっと一周しただけでなんと11種類もの街路樹に出会いました。
お弁当タイムをはさんで、次は押し葉づくりです。
時間が経つと葉っぱがクタクタになってしまうので、ぜんぜんから押し葉の作り方を教えてもらって挑戦しました。

まずは新聞紙を一枚ずつに剥がして、3回折って準備します。
一つ開いたところに葉っぱを挟んでいきます。
そして、「挟んでいない新聞紙→葉っぱを挟んだ新聞紙」を繰り返して交互にセットしていきます。
重なった束を段ボールで挟んでゴムで縛って持ち帰ります。
家では、毎日葉っぱを挟んでいない新聞紙を抜き取り、新しい新聞紙を入れるという作業を行い、水分をしっかり取ります。
こうすることで、何年経ってもきれいな押し葉ができあがるそうです。
そんなわけで、次回まで自分の押し葉をしっかりお世話してくるという任務が!
押し葉の準備ができたところで、次は図鑑を使って名前を調べる「同定作業」です。

机の上に置かれた人数分の図鑑を見るなり、まるでマンガでも読むように夢中で図鑑に見入っていました。

ぜんぜんが話をする前から、葉っぱの形で検索してみたり、自分なりに同定している人もいました。

みんなで、1種類ずつ特徴を確認しながら図鑑で探します。
「これだと思う!」と予想を発表し合いながら、進んでいきました。
「これとこれ、どこが違うの~?見た目一緒だよ~」の声に、ぜんぜんが説明をしてくれます。

「羽状複葉」「重鋸歯」なんていう難しい言葉も出てきましたが、さすがは小さな研究者たち!
一生懸命話を聞いて、メモしていました。

図鑑の見方も少しずつ慣れてきて、「この葉っぱはイタヤカエデだと思う!!」という意見に、ぜんぜんから「正解!」の声!
11種類全て調べきりました。

この日の活動はここまでで、1日を振り返って感想を話し合いました。
「葉っぱの形は全部でどれくらいあるのか調べたくなった」
「図鑑で調べることが面白かった」
「グループの子と仲良くなれたのが嬉しかった」
「ハクウンボクの皮をむいたらいいにおいだった」
「葉っぱの種類がいっぱいあることを初めて知った」など発表してくれました。
今日はこれで終了!かと思いきや、ぜんぜんが話してくれた植物の「生き残る」話にみんな夢中!
次々質問も飛び出して、面白い時間となりました♪
さあ、話の続きはまた次回ね!ということで1日目が終了しました。
次は、家でお世話した押し葉を使って図鑑を作ります!!
どんな押し葉が出来上がっているか楽しみです★
環境プラザスタッフ(N☆)